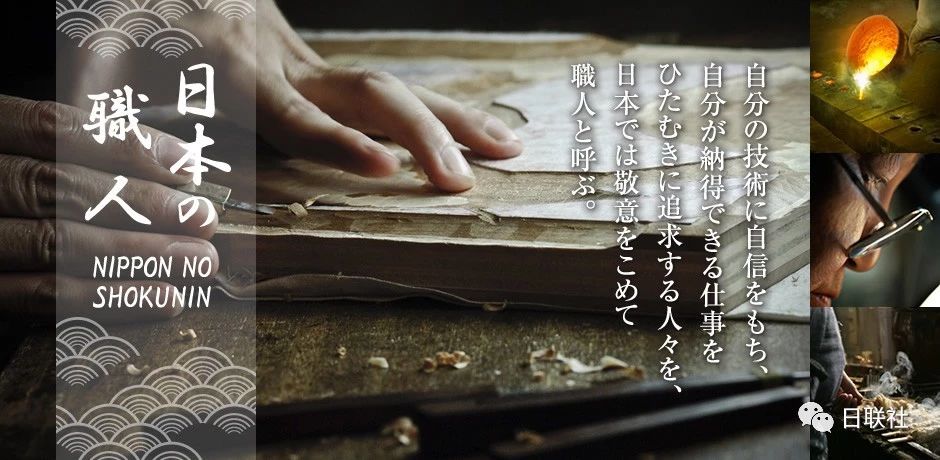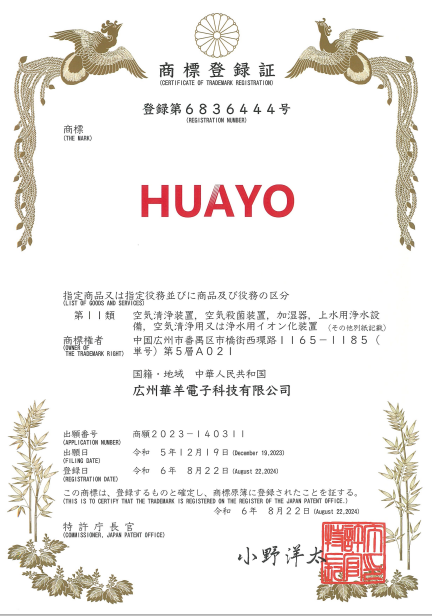日本中国文化交流協会とは
創設
1956年3月23日、中島健蔵(仏文学者)、千田是也(演出家)、井上靖(作家)、團伊玖磨(作曲家)らが中心となり、日中両国間の友好と文化交流を促進するための民間団体として東京で創立されました。その活動を通じ、日中国交正常化の実現や日中平和友好条約締結に向けての国民世論の形成に寄与しました。日中両国の文化交流を通じて、友好、相互理解をいっそう促進するため、活動を続けています。
組織
会員制。会員は文学、演劇、美術、書道、音楽、舞踊、映画、写真、学術(自然科学、人文社会科学)など文化各界の個人、出版、印刷、報道、宗教、スポーツ、自治体、経済界などの団体・法人を中心とします。
催しのご案内はこちらから
活動・業務
創立以来、文化各専門分野の交流のための代表団の相互往来を中心に、舞台公演、映画会、音楽会、文物・美術・書道など各種展覧会、学術討論会の相互開催などの活動を展開しています。その活動が評価され、下記の6賞を受賞しました。
・朝日賞 1973年(昭和48年)朝日新聞社
授賞理由 長年にわたる日中文化交流への貢献と日中国交正常化への貢献
・国際交流奨励賞 1985年(昭和60年) 国際交流基金
授賞理由 日中文化交流を通じて、両国の相互理解増進に尽力
・中日文化賞 1987年(昭和62年)中日新聞社
授賞理由 中国との文化交流への貢献
・井上靖文化賞 1997年(平成9年)井上靖記念文化財団
授賞理由 創立以来40年間にわたる、日中文化交流への貢献
・文化交流貢献奨 2007年 (平成19年)中華人民共和国文化部
授賞理由 中国との文化交流への貢献
・中日友好貢献奨 2010年(平成22年)中国人民対外友好協会 中国日本友好協会
授賞理由 日中友好の促進に貢献
月刊誌
『日中文化交流』を毎月一回1日付けで発行
![]() 一般財団法人 日本中国文化交流協会
一般財団法人 日本中国文化交流協会
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビルヂング423区
TEL:03(3212)1766 FAX:03(3212)1764
JAPAN-CHINA CULTURAL EXCHANGE ASS.
新しい年の新しい意味(NO.825 2015.1.1より)
日本中国文化交流協会会長
黑 井 千 次
二〇一二年の尖閣諸島をめぐる問題の発生以来、日中両国の関係は悪化を続け、きわめて不安定な状態のまま月日が流れている。このままではどうなってしまうのか、と憂慮していたある日、日中文化交流協会の事務局職員として、一貫して両国の文化交流の仕事に取り組み続けて来た人に会った。年齢のこともあって今は事務局職員を退き、本協会の役員を務めている男性である。
こんな状態が続いて、この先どうなるのだろう――そう問いかけずにいられなかった。
ゆったりと笑みを浮かべたその人は答えた。これまでには、もっとひどい状態の時期がありましたよ。それを乗り越えてここまで来たのだから、大丈夫ですよ、今度も。しっかりと取り組んでいきさえすれば、行く手にきっと光は見えて来ます――。
日中国交正常化の時期から同じ仕事に携わって来たその人の言葉の内には、波風を孕みながらもゆったりと流れ続ける歴史の時間の横顔のようなものが隠されているかに感じられた。個々の出来事に一喜一憂するのではなく、より高い視点から、全体の流れを過たずに掴むことが出来たなら、この先の眺望を得ることも可能であるのかもしれない――不安を抱きながらも、その人の自信たっぷりの言葉に、ほっと息をつくことが出来る思いを味わった。
また、こんなこともあった。日中関係に深い関心を寄せるある政治家が、我々の仕事として日中関係改善に取り組んで、今具体的な仕事を進めることはなかなか難しいが、文化交流の営みにはそういった障害がないだろう。だからその方面の仕事に取り組んでいる人達は、今可能な文化交流の仕事を積極的に進めてもらいたい、と。
政治家というものが政治的事情の中で動かざるを得ないのは当然であろうけれど、そして政治が問題を抱えて動きが取りにくくなった時、文化交流面の友好を少しでも進めてもらいたいと考えるのは自然であるのかもしれないが、ただ「政治」と「文化」とを同じ盤の上で動かすゲームの駒の如くに扱う考え方がもしあるのだとしたら、ことはそう簡単ではないことを認識する必要があるだろう。「政治」と「文化」は別のものでありながら、どこかで深くつながっている。人類の長い歴史の中で、政治の結果が文化となり、また文化の力が政治を動かすことも考えられなくはない。
文化交流が良好な状態で進められている時には、そのあたりの事情は見えにくくなっているのかもしれない。
しかし国際関係に問題が生じて交流も進みにくいような困難な状況の中でこそ見えてくる課題があり、それへの取り組みが求められているともいえよう。
明けた年を、困難を乗り越えつつそこに新たな課題を発見し続ける、力のこもった年として受け止めたい、と祈念せずにいられない。〈くろい・せんじ 作家〉
今からでも遅くはない
(戦後70年特集NO.832 2015.8.1より)
日本中国文化交流協会副会長・理事長
池 辺 晋 一 郎
残念ながら先年逝去された元駐中国日本国大使・中江要介氏にはいくつもの名言があるが、今も印象に残っているのは次のような言葉。「日本が近隣諸国に対し戦後すぐに謝罪を行なっていたら、東アジアのその後の展開は違ったものになっていただろう」。
僕がこの小文を書きかけたころ、本誌の前号(No.831)が届いたのだが、その最初のページの井出孫六常任委員(作家)の文章を読み、実は驚いた。戦後ドイツの歩みかたについて、僕も書きかけていたからだ。従って井出氏と重複するかもしれないが、そのまま貫徹することをお許し願いたい。
旧西独で1969~74年に首相の地位にあったヴィリー・ブラント氏は70年にポーランド・ワルシャワのゲットー英雄記念碑の前に跪き、花を捧げた。
その次代の首相、ヘルムート・シュミット氏が国連で行なった演説の大意はこうだ─「戦後、長い時が経った。しかしドイツが再び過ちを犯さないと確約するには、まだ、短い」。
そして昨年6月、北フランスでの「ノルマンディー上陸作戦70周年式典」にヨーロッパ各国首脳が集った。何とそこに、現独首相アンゲラ・メルケル氏も並んでいるではないか。テレビの映像に、僕は驚愕した。
メルケル氏は、イスラエルへ赴き、ユダヤ人への謝罪をすでに行なっている。先の大戦に関し、「すべてのドイツ人は永久にその罪を負う」という発言もしている。
驚愕と同時に、たとえば中国のどこかで終戦○周年記念行事が挙行されるとして、そこに日本の首相が列席している図を想像できるか、と僕は自問していた。
閑話休題。僕は、日本のベテラン女優たちが毎夏につづけている朗読劇「夏の雲は忘れない」の音楽を担当しているが、「ヒロシマ・ナガサキ1945年」というサブタイトルを持つこの劇は、被爆児童の詩を中心に読まれるもの。すなわち、被害の記憶である。
いっぽう僕は、84年に作曲した混声合唱組曲「悪魔の飽食」に全国の人が集い「全国縦断コンサート」をつづけている際の指揮者でもある。国内のみならず、すでに2度の中国を含む6度の海外公演を成功させてきた。この9月にはハルビン郊外の「731記念館」リニューアル式典に招かれ、300人近くがそこで歌う。これはすなわち、加害の記憶だ。
被害と加害の双方の記憶を語り継がなければならない。このバランスは極めて重要だ。加害の罪を語ると自虐的史観という人がいるが、謝罪が自虐につながると考えることこそ奇妙だと僕は考える。
戦後70年。戦後の史観に恒久的でよりよいバランスを与えることが、今年に課されていると思う。前記の中江氏はバレエ台本作家という文化人で、僕は3作でコンビを組んでいる。かつて日中国交回復が卓球で始まったように、文化が日本及び東アジアに正しい史観をもたらす芽になるかもしれない。中江氏が生きていらしたら、「今からでも遅くはないよ」とおっしゃるのではないか、と思うのである。〈いけべ・しんいちろう 作曲家〉
創立六十周年にあたって
(NO.837 2016.1.1より)
日本中国文化交流協会会長
黑 井 千 次
今年は当協会の創立六十周年にあたる。この歳月は日本と中国との古来よりの交流の歴史を振り返れば、束の間であるとしても、人間でいえば還暦にも相当する節目の年である。
そしてその間、建国以来の新しい中国を日本政府が認めようとせずに往来が容易ではなかった時期、文化大革命によって中国の国内が混乱していた時期、国交が正常化して様々な交流が花開いていった七十年代後半、その後も歴史認識や領土問題が生じ、この歳月も決して平坦なものではなかった。双方の政治や経済の変化もあった。それを顧みれば、よくぞ折々の困難や様々の障害を乗り切って今日まで来ることが出来た、と思わずにいられない。創立時、会員の会費で運営する民間団体のわが協会が、六十年も存続すると思った人は一人もいなかったのではあるまいか。
今日の日中文化交流協会があるのは、協会の趣旨に賛同して支えて下さった会員の皆様の支持と協力、折に触れ協会の活動を支援して下さった各界、各層の方々、そして交流の相手方である中国関係方面の皆様の心温まる対応があったからこそである。この節目の年にあたり、それらの方々にあらためて心からの感謝の意を表する次第である。
また、協会の先頭に立って指導された中島健蔵、井上靖、團伊玖磨、辻井喬ら歴代会長や役員諸氏の努力、創立以来一貫して歴代会長を支え続けた事務局長の白土吾夫氏、その白土イズムを継承している事務局の日々の仕事の積み重ねがあったことも忘れてはならない。
ここ二、三十年ほどの間に、内陸と沿海部に発展の差はあるとはいえ、中国の人々の暮しの様相や街並みが激変している。昨今の両国関係の悪化にもかかわらず、中国からの観光客の激増の動向を見ても、両国の関係は質的に変化して来ていることがうかがわれ、そして今後も更にダイナミックな変化を遂げていくだろうことが予想される。そしてその動きの中で、文化の役割はますます重要になっていくに違いない。これまで六十年の交流の歴史は、今後も起きるであろう様々な困難や問題に対処する際の貴重なヒントになるし、また新たな交流を創造していく上での頼りになる財産ともなるだろう。
人は変り、社会構造も変化していく。当協会も先人の精神を受け継ぎながら、時代の変化にしなやかに対応していく柔軟性が一層必要となるに違いない。
今年、創立六十周年を記念する各種展覧会、各分野の代表団、訪問団の相互往来など、様々な事業・企画の準備が、関係方面の団体、個人の理解と協力を得て進められている。それらの一つ一つが成功し、文化交流の果実として稔り、更には貴重な歴史として今後に伝えられることを願わずにいられない。
<くろい・せんじ 日本藝術院院長、作家>
新しい年に向かって
(No.850 2017.1.1より)
日本中国文化交流協会会長
黑 井 千 次
日中文化交流協会は、昨年の創立六十周年の節目を経て、次の新しいステージに向かって第一歩を踏み出そうとしている。
この一年の交流は、長く育て続けて来た各界代表団の定期的訪中、同じく中国側代表団の来日、というこれまでの相互訪問という基本的な活動を維持、展開することが出来た。
その上に、記念すべき年にあたって、栗原小巻氏(副会長)の一人芝居の北京公演、前年に続く総勢九十名に及ぶ日本の大学生の訪中と中国の大学生との交歓や意見交換、鑑眞和上像の東渡記念行事などが行なわれ、日本では、「漢字三千年」展の開催が実現した。
日中両国の政治・外交関係が、領土問題や歴史認識をめぐって必ずしも滑らかには運んでいない今日、以前と同様の密接な関係を維持し続けるのにはそれなりの努力が必要ではあるだろう。しかし当協会のメンバーが中国の関係者と顔を合わせて語り合う時、そこにはかつてと変わらぬ親しみや温もりが漂っていた。これが六十年の歴史が生みだした力によるものか、とあらためて感じぬわけにはいかなかった。そして文化交流の営みは、政治や外交や経済の動きとは別なのだから、両国関係が滑らかに進まぬ時も積極的に活動を展開してくれ、といった協会外部の意見に接する度に、文化交流の力が、どこかで政治や経済の営みにも影響を与えるようにはならぬものか、といった夢の如きものが生まれてくるのを覚える。
英国のEU離脱の動きや、アメリカの大統領選挙の動向などを伝えるニュースに接する度に、世界は今や大きく変りつつあるように感じる。地震や津波、原発事故といった大問題を抱える日本も、この先どう生きるか、を深刻に摸索せざるを得ない地点に立っている。そして中国も、様々な問題を抱いたまま、この先の進路を懸命に探っているかに見える。
そのような時代、情勢、環境の中をどう生きるかは、国を超え、民族を超えて人類が取り組まねばならぬ課題であるに違いない。その中の一つの大切な繋がりとして、日本と中国の関係、結びつきは歴史の場で確かめられていくに違いない。
日本中国文化交流協会の、六十年を経て新しく迎えるこの年は、希望に満ちているなどとはいえまい。しかしそうであればあるほど、希望を求め、希望に向かう道を探り続けることが求められているといえよう。その営みの一年がここに始まったのだ、とあらためて感じる。
〈くろい・せんじ 作家、日本藝術院長〉
本当の友情
(No.857 2017.8.1より)
日本中国文化交流協会副会長・理事長
池 辺 晋 一 郎
何度、中国へ行っただろう……。初めて行ったのは1985年11月。杉村春子団長のもと数人の旅だった。その折「私、ちょうど30回目なのよ」と言う杉村さんの記憶力に感嘆したが、いっぽう、よく考えなければ回数も分からない自分に、今いささか苛立っている。
映画人代表団や音楽家代表団があった。また、日本の現代音楽を披露するという国際交流基金の企画で、弦楽四重奏団とともに幾つかの都市を回ったこともある。北京中央音楽院で特別講義をしたこともある。
そして1986年の「日中合作バレエ」。当時の駐中国日本大使(故)中江要介氏はバレエ台本作家としてすでに僕と2作を協働していたが、その3作目として「蕩々たる一衣帯水」という作品を書かれた。中国の作曲家の友人・葉小鋼氏と僕が分担して作曲。北京と東京で上演した。
だが、僕の訪中で最も重い意味を持つのは、3度にわたる合唱組曲「悪魔の飽食」公演だと考える。先の大戦間に、日本陸軍が旧満州・哈(ハ)爾(ル)賓(ビン)郊外に構えていた731部隊がおこなった捕虜への凄惨な人体実験の記録。その全容を明らかにした森村誠一氏の著書をもとに、1984年、僕は7章から成る混声合唱組曲を作曲。そのとき僕はこう考えた――戦争を語り継がなければならないとよく言うが、それは原爆や空襲など「被害」についてのみでいいのだろうか?被害と同時に「加害」を含むのが戦争だ。その事実を放置してはいけない。この「悪魔の飽食」には、戦争が引き起こした狂気と罪への弾劾の血がにじんでいる。作曲しなければ……。
初演から何年か経って、新たな驚きがやってきた。この曲を歌いたいという人が大勢現れ、ついに1995年から「全国縦断コンサート」が開始されたのである。毎年どこかでコンサートが催され、その都度の地元に加えこれまで歌った人たちが全国各地から集合。今年は27回目で、7月2日、名古屋。総勢370人。ステージいっぱいの大迫力だった。
さらに、これまで7度の海外公演。うち3度が中国である。北京、南京、瀋陽そして2度の哈爾賓。これらの旅の途上、731部隊跡はもちろん、南京大虐殺や平頂山事件の現場も訪れた。あの戦争の侵略や加害に関して日本国民が深い謝罪の念と反省を抱いていることを、中国の人たちへ伝えたかった。民間の日本人が日本政府とは異なる意識を持っていることを、中国の人たちへ伝えたかった。
ベテラン女優たちが広島・長崎の記憶を読む朗読劇「夏の雲は忘れない」の音楽を僕は担当し、毎年の公演に関わっている。これは「被害」。そして「悪魔の飽食」に代表される「加害」を併せることで、戦争を語り継ぐことのバランスを形成しうると僕は考えている。戦後レジームからの脱却と為政者は言うが、勝手に脱却を標榜することは許されない。戦争を真に乗り越えたところにこそ、日中の本当の友情が存在すると思うのである。
<いけべ・しんいちろう 作曲家>